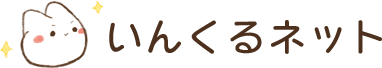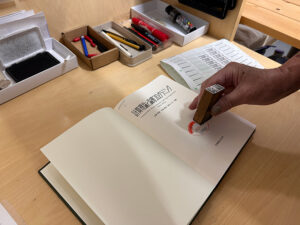改良メダカについて
改良メダカとは、ニホンメダカを観賞用に品種改良したメダカです。
メダカは変異性が高く、現在様々な愛好家によって交配が行われています。
メダカは日本で1番小さな淡水魚です。めだかを漢字で書くと「目高」となります。これは、目が体の高い位置にあることを意味しています。実際にめだかの目は視力が良く水面近くで流れてくる餌を見張っていて、口は水面に浮いたえさを食べやすいように上向きについています。顔を横から見ると目の位置や水面のものを食べやすい形になった口など様々な特徴を持っている事が判ります。

メダカは18世紀頃より鑑賞用として飼育されたと言われていましたが、19世紀頃にはメダカよりも派手な金魚の方が人気となり観賞用としてのメダカの人気は衰えました。
しかし近年メダカ愛好家による改良品種が盛んになり、様々な改良品種が誕生し、愛好家達による品評会が開かれてます。
メダカは飼育が簡単なことと繁殖サイクルが早く品種改良や繁殖を目的とする方も多いですが鑑賞用としても人気が浸透しています。
自宅で飼育を楽しむ愛好家が急増する一方、改良メダカが全国の河川などで相次いで発見されています。これは飼育が困難になって野外に放流するケースが多いとみられています。
観賞用メダカは在来種との交雑などで各水域の生態系を脅かす恐れがあり、専門家らは国内外の外来種に続く「第3の外来種」として警戒を強めています。
改良メダカを無料で引き取りしている団体も各地に多数ありますので、改良メダカを飼いきれなくなってしまった場合は相談してみましょう。